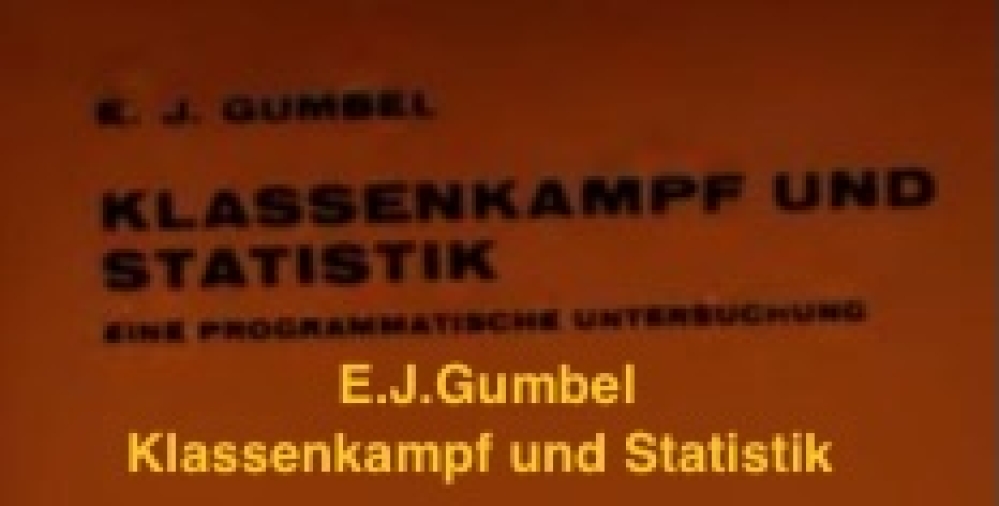
本稿は、杉森滉一・木村和範編著『統計と社会経済分析2 統計学の思想と方法』、2000年、北海道大学図書刊行会(現:北海道大学出版会)刊行、ISBN4-8329-2821-X/2000/A5判・320頁・3800円(税別)、に所収されたものの原稿である。同書所収の論文とは,違いがあるので,本稿から引用するときには,[電子版]と明記して下さい。山田 満 2009年8月23日
2010年10月一部訂正
「統計利用者の統計学」から「公民権のための統計学」へ
------ B. ヒンデスの官庁統計論との関連で ------
山田 満
はじめに
本稿の目的は、B.ヒンデスの統計論を蜷川統計学の諸テキストと交差させながら社会科学認識論(歴史的認識論)のパースペクティブから「兆候的に読解し」(アルチュセール)、ヒンデスが今日の社会科学的統計学の統計論にたいして提起している問題とその限界を確定し、その積極的な問題提起と限界を《統計利用者の統計学》から《公民権のための統計学》という統計学の構想へと至る通路のなかで開いていこうとする試みである。かつて蜷川統計学は、統計学を《統計利用者の統計学》として再構成することによって、統計学に新しい問題の次元を与え、統計学に社会科学としてのアクチャリティーを回復させたが、今日、われわれが直面している諸問題・諸困難にたいして社会科学としてのアクチャリティーを統計学に回復するためには、蜷川的な意味での《統計利用者の立場》を超え出たところに理論構築の足場を築かなければならないということを本稿は主張したいと思う。
I. 蜷川統計学からヒンデスの官庁統計論へ
ポストマルクス、ポストアルチュセール派(注1)の代表的な政治理論家として知られるバリー・ヒンデスは、リバプール大学の社会学講師であった1973年に『社会学における官庁統計の利用』(注2)という小冊子を書いている。官庁統計の解説書の域を超え、その誤り偏向を指摘し、その誤用を是正し「正しい」利用の在り方を提起する文献は多いが、官庁統計の基本的性質を統計データ生産の原理的次元にまで遡って検討し、その認識論的価値を「合理的に」評価しようとする試みは意外と少なく、同書は、そのような根源的な問題を提起した書物として、その後の、英語圏における官庁統計データ論や統計データ生産・利用論の議論の一つの方向を決めるうえで重要な役割を果たしてきた。英国では、1970年代の後半に《ラジカル統計学(RADSTATS)グループ》という社会統計学(社会科学統計学)の革新を目指す運動が形成されたが、その統計論の形成に同書の問題提起は大きく寄与したのである(注3)。他方、第二次世界大戦後の日本語圏での社会統計学の官庁統計論・統計データ生産論を支配してきた統計学の言説は蜷川統計学であったが、ヒンデスの統計論は、蜷川統計学の言説との対比でも興味深い論点を提示している。そこで、ここではヒンデスの統計論の特徴を蜷川統計学との関連で見ていくことから始めることにしたい。
1. 統計利用者のための統計学
レイ・トマスも指摘しているように現代社会科学の領域に属する社会調査研究方法論の多くは、データは利用者自身によって作られるという前提の上に書かれている。そこでは官庁統計をはじめ既存の統計データに基づく調査研究は、社会科学的な事例調査・参与観察・標本調査などの本格的な研究調査を行うための準備段階として位置づけられ、調査研究の対象領域の区画設定・概要把握を行う調査研究段階と見なされる傾向がある。その結果、人文科学の分野において研究方法上で重要な位置を占める文献考証や資料考証に対応するような《統計データ考証》のような研究は他と比べて軽視されてきたように思う。主に官庁によって作られる統計データは、他者(官庁)の関心によって作られたものであり、「社会学者達にとってそれほど意味あるものではないかもしれない」といった一般的な指摘で満足してしまいがちだったのである。その結果、統計や統計調査に対する関心は他の学問分野とされてしまうか、社会科学内部の異端派が取り上げるようなマイナーな問題領域とされてしまうことになったのである(注4)。
ヒンデスの官庁統計論が介入したのは、このような今日的な状況のなかにであった。ヒンデスは、官庁統計の資料としての性質を社会科学的研究の対象として問題設定し、きちんと分析・検討しなければならないと主張したのである。こうしたヒンデスの主張の背景には、リバプール市の労働党の支持基盤の社会学的構成の変化を分析した彼の出世作である『労働者階級政治の後退』に結実する政治社会学的な研究の経験があったことは想像に難くないが、ここで強調しておきたいことは、1960年代後半から70年代にかけての欧米諸国における「マルクス・ルネッサンス」、なかでも《アルチュセール的旋回》との関連である。マルクス主義に基づく研究は、社会のミクロな研究に満足することなく、社会の全体論的で理論的に首尾一貫した研究を要求したからである。ヒンデスは、当時、《理論的実践グループ》というアルチュセール理論の研究と普及を目指したグループに所属しており、レーニンの『ロシアにおける資本主義の発展』を理論的範例(パラダイム)とした社会の分析を目指していたのである。そのような社会の分析には、レーニンの場合がそうであったように、官庁統計の利用が不可欠であり、官庁統計の資料としての性質を官庁統計家とは異なった立場から批判的に分析する研究が不可欠だったのである。経済学においては、とくにケインズ経済学以降は、国家の経済・社会の総過程に対するマクロ政策的管理という観点が前景に出たことにより、経済・社会の全体論的把握への要求が高まり、官庁統計に対する関心も高く、官庁統計の不備や誤りや経済実態からのかい離に対する批判は常態化したが(注5)、その関心は官庁統計の作成者でもある国家による経済の総過程のマクロ政策的管理というコンテクストのものであり、官庁統計の成立地盤そのものを「他の立場から距離を置いて」問い直し、批判的に分析していこうという問題関心は生まれなかった。そこにヒンデスの官庁統計論の大きな意義のひとつがあったのである。
こうしたヒンデスの立場は、蜷川統計学の立場と比較したときに興味深い一致を示す。周知のように、蜷川統計学は《統計利用者のための統計学》として自らを特色づけていたからである。今日、蜷川統計学に他の統計学と区別する独自性を与えているものは、それがドイツ社会統計学の批判的な読解から形成されたということである。西欧における資本主義後進国ドイツでは、学問も「上からの国家主導型の資本主義化」のために動員されたが、社会統計学も例外ではなかった。ドイツでは、英国のように資本の運動領域の自律性を確保するために《社会的なもの》から《経済的なもの》の領域を明確に分離しなければならない理由は少なく、経済は社会のなかに埋め込まれた形で理解され、社会学のなかで語られる傾向が強かった。そのため、社会学は国家主導の上からの資本主義化のための国家の政策に奉仕する官学としての側面を強く持ち、国家の政策画定に深く関わった。こうしたなかで統計学は、ドイツ国情論の《State-tistics》(注6)としての側面を強く引き継ぎ、国家権力と結びついて国家の状態(国力=国勢)を数量的に調査・記述し、社会生活のなかに一定の規則性(合法則性)を見つけることを目的とした《社会学の一領域としての統計学》(社会統計学)として形成されたのである。ドイツ社会統計学が、官庁統計家のための統計学であり、国家・官庁統計家と利害・関心を共にした社会研究者のための学としての性格を強く持ったことは、当然であったのである。蜷川統計学は、このようなドイツ社会統計学から統計調査に関する方法についての学という側面と、社会研究の方法論としての側面を継承しながら、その官学としての側面を批判し、国家権力とは利害・関心を異にした統計利用者の利害と関心を反映した学問として統計学(社会統計学)を再構築しようとしたのである(注7)。ヒンデスの統計論と蜷川統計学との間には興味深い共通性があるのである。
2. 統計生産の理論と唯物論の哲学
ヒンデスの統計論は英国社会学会の後援を受け英語圏社会学における諸論争・諸難問への介入を意図してマクミラン社から刊行された「社会学における諸研究」(A.ギデンス主宰)というシリーズに収められたもので、英語圏社会学のコンテクストのなかで、社会学における官庁統計論の系譜の延長線上に書かれたものである。そのため、ヒンデスの統計論は、英国(英米)社会学主流派と異端派の各々の官庁統計観に対する位置取りという形式的制約下で叙述されている。ヒンデスは、この位置(陣地)取りを哲学・社会科学方法論の戦場で行い、主流派の経験論的実証主義と異端派の社会現象学・エスノメソドロジー・認知社会学との対抗関係という形式のなかで行っている。
ここで経験論的実証主義は、認識の絶対的な基礎を感覚によって与えられるイメージの束としての経験に置く考えで、世界は感覚によって与えられたもの以外ではなく、その感覚によって受容される世界のイメージ(経験)は世界の「正しい」像を写しており、「観察言語」はそれを「正しく」言語表現化することができると考える科学認識論上の立場である。この考えに基づけば、すべての理論的な言明は観察言明に還元される必要があり、還元されて初めて言明は意味をもち、真偽の判定を受ける。この意味で理論的労働は、観察や経験という行為にたいして従属的な地位に置かれ、それ自身で意味を作りだし真偽を作りだすという独自性を与えられていない。この考えでは、結局のところ 認識は経験に還元されるのであり、経験は実在の世界の事実を「正しく」写すとされるのだから、認識の内容(真実)は実在の世界のなかにあることになり、認識過程は実在の世界のなかに既に実在している真実を取りだし、写しだし、言語表現化する過程だということになるのである。社会学における官庁統計利用の古典的範例はデュルケイムの自殺論(分類と比率の研究)であるとすれば(注8)、経験論的実証主義は、「自殺」という事実は認識過程に先立って実在の世界のなかに事実として存在しており、官庁統計は様々の技術的な問題や定義付けの問題などを含んでいたとしても、それらは修正可能であり、克服でき、「自殺」という所与の客観的事実を体系的に観察・記録し写し取ることができると考えるのである。結局のところ、官庁統計としての自殺統計は、経験論的実証主義にとって、「所与の事実」なのである。
それに対して、社会現象学やエスノメソドロジーは「自殺という所与の事実」の「所与性」を問題とする。ある事象を一定の手続きにしたがって観察したとして、その事象を「自殺」として認知し記録することは自明なことではない。何を「自殺」としてカウントするかは「道徳的・社会的な省察」に依存することで、道徳的・社会的省察は時代と地域と社会集団の違いに応じて、さらに個々人の性質に応じて様々であろう。また、学者が行う定義と統計調査などに用いられる経験的・行政的(法律的)な定義とが同じであるとは限らないであろう。さらに、仮に定義問題が解決したとしても、「自殺」を隠そうとする社会的・道徳的理由が存在し、それを隠す諸手段も多様にあり、しかも、それを隠す諸手段は社会的に均等に配分されていないだろう。経験論的実証主義は、こうした問題の所在を認めないわけではないが、そうした問題は「公正な論議と同意の形成が調達できれば」克服でき、「(間主観的な同意という意味で)客観的な」定義づけが可能であり、「(間主観的な場に成立する)観察言語」(ないし、その代用品)による「事実」の記述に基づき、「事実」の「客観的」記録は可能だという立場をとるのであるが、社会現象学やエスノメソドロジー(認知社会学)は、そのような戦略はとらず、経験論的実証主義においては正確な観察とデータ分析のために解消されなければならないと考えられる問題のすべてが解消されるべき問題でも、現実に解消できる問題でもなく、自殺という社会的事象の解明にとって重要な社会的意味をもっていると考えるのである。「自殺」という言葉の周りで語られる事柄や行われる行為のすべてが社会的世界(日常的世界)のなかで生きている行為者にとって意味をもっており、その意味を解読することが「自殺」という「社会的事実」を社会的行為者たちがいかにして作り上げ、その「事実」といかにして向き合って日々の生活を生きているのかを解明することを可能にするのである。社会現象学やエスノメソドロジーにとって「社会的事実」は「所与」ではなく、社会的行為者たちの日常的な行為と意味付けによって「構成」されるものなのである。このような考えのなかでは、官庁統計は「所与の事実」を観察し記録するものというより、世界の事実性を「構築」する装置として見なされ分析されるであろうし、統計調査に特有な観察形式、たとえば限られた数の質問を定型的な質問文で行わなければならないという形式上の制約が複雑で多様な社会的世界を「平板化」してしまうということが問題として指摘されたりするであろう。
ヒンデスの統計論は、このような官庁統計を巡る社会学論争のなかでの位置取りを課題として叙述された。そのため統計論としては、官庁統計論のなかの限定された問題領域を限定した問題に限って、しかも「認識論的・方法論的な」問題に絞って論じているに過ぎず、統計基礎論としての社会集団論を土台に調査論と利用論を一貫した立場から論述していこうという蜷川統計学のような体系性は持っていない。その意味で、ヒンデス統計論は蜷川統計学の代替案ではあり得ない。にもかかわらず、ヒンデス理論には蜷川統計学を現代に通用する学問として再生していくことを可能にする重要な要素が含まれているように思われる。その要素とは、唯物論の哲学を基礎とした統計生産の理論である。
ヒンデスが「官庁統計は生産物として分析されなければならない」とテーゼ風に書くとき、そこで意図されていることは経験論的実証主義と社会現象学・エスノメソドロジー・認知社会学との間での位置(陣地)取りである。ヒンデスはこのテーゼを立てることで論弁上の立場と権利を確保しているのである。生産物であるかぎり、(官庁)統計は一定の生産過程によって一定の素材を加工した結果と見なされなければならない。既に与えられている所与の事実を単に数え上げ・計測する過程ではあり得ないのである。官庁統計の生産は生産過程であるかぎり、社会体のなかに存在し、社会体に対して現実的な効果を産出する過程でなければならず、経験論的実証主義が想定するような「所与性」(観察言明という間主観的な経験性の場への認識の還元)を前提にした議論をすることはできない(ある人の死を官庁統計が「自殺」としてカテゴライズし、自殺統計を作成し公表することは、既に確定的に存在している「自殺」という事実を単に記述することではなく、それ自身独自の社会的効力を持った社会的過程であり、むしろ「自殺」という個人的・社会的事実の生産に構成的に関与していると考えるべきなのである)。他方、生産物であるかぎり、官庁統計はそれを生産する合理的に解明可能な社会的・制度的な過程、機構をもっているはずであり、社会現象学やエスノメソドロジーが考えるように統計の作成と利用の過程を観察者・被観察者や社会的行為者などによる諸事象への意味付与(志向性)の場に、換言すれば、社会的諸主体間の《主観性(志向性)》の闘技場に官庁統計の問題を還元してしまうことはできないのである。そのような場には還元できない自律性と合理性を官庁統計の生産過程は持っているのである。
このように、ヒンデスの官庁統計論の核心にあるのは、統計データの生産の理論である。しかし、蜷川統計学においても「国家は統計の......最大の生産者である」とか「(統計は)調査とよばれる歴史的な実践によって得られた....歴史的な産物である」(注9)という表現に示されるように、生産・生産物・産物という言葉は頻繁に用いられている。だとすれば、ヒンデスの統計生産論の特徴を蜷川のそれとの関連で明確に定義し、種差を明確に定義する作業が必要となろう。
2-1)蜷川統計学の統計生産の理論と唯物論
大橋隆憲が書いているように、「蜷川理論は......、社会的集団=大量を統計学の基本概念とし、これから統計方法の一切の問題を展開することを理論的要請としている」(注10)。大橋のこの言明は大変優れたもので、基本概念からすべての概念を論理的派生物として導出するというヘーゲル派マルクス主義の体系構成法を念頭に置いたものである。「客観的存在」である社会的集団が「統計数(表)」という形象で自らを表出し、社会の統計的法則性(規則性)という形象で自らの存在を「客観的に」総括する過程を統計方法論(調査・利用の規範的手続き論)という形式的枠組みのなかで叙述すること、これが蜷川統計学の課題であり、独自性だったのである。蜷川理論は、このような過程を叙述したものに「客観的方法」という名称を与え、すべての「実在の」統計活動が,それに照らして「客観的に」評価される基準となる「規範的方法」としての地位を与えた。すべての「実在の」統計活動はこの規範的方法に沿って行われることを要請され、それができない場合には「信頼性」と「正確性」に問題が出てくるとされたのである。蜷川統計学の官庁統計論は、官庁統計(と官庁の統計活動)をこの規範に照らして評価し、社会科学的認識のための素材としての官庁統計の性質を検討することを課題としたのである。
その際、蜷川統計学が力点を置いたのは、官庁統計(官庁の統計活動)の社会的批判(批評)であった。蜷川統計学は、1930年代の前半にその体系的構築を完成させたが、その時代背景を受けて、「内」に向かっての国家総動員体制の構築と「外」に向かっての帝国主義的・植民地主義的拡張とに連動した国家の情報装置(情報収集・蓄積・利用の装置、及び情報統制装置)の作動の一環としての統計装置の作動に注意を向け、統計情報の収集と利用の過程が国家に独占され、「一般民衆」(蜷川虎三)の統計にたいする要求から切り離された「疎遠」な存在になってしまっていることを批判したのであった。蜷川統計学は、このように《国家に抗する一般民衆》の立場に立ち《統計利用者のための統計学》を構築したのであるが、そこで「一般民衆」の統計に対する要求として定義されたことは「 統計の与える内容が社会的・客観的なものでなければならない」(注11)ということであった。ここで「社会的」とは為政者の利害だけでなく一般民衆の関心・利害をも反映した普遍的・一般的利害を体現した統計の作成ということであると共に「情報の公開性」を意味していると考えられ、また「客観的」とは為政者の利害によって歪められない「正しく」事実を反映した統計を意味していると考えることができるが、いずれにせよ蜷川統計学においては、(官庁)統計論の問題は「社会的、客観的」な利害関心を反映した正しい認識内容をもつ統計を作成し活用することであり、その「正しい」作成と利用を妨げる要因として為政者=国家の利害関心(認識関心)が考えられたのである。第二次大戦後の蜷川統計学が特に力を入れて継承したのは、こうした蜷川統計学の官庁統計(官庁の統計活動)の社会的批判(批評)の側面であった。戦後蜷川統計学は官庁の統計活動が信頼性と正確性を持ちえない原因をその社会的条件に遡って解明し、官庁統計活動の「是正」(ないし「民主的改革」)の方途を探ることを課題としたのである。そこでは、統計の生産者であり、最大の利用者でもある国家(行政機関)の性質が注目され、官庁統計の生産者であり利用者である国家の関心・利害(主観性)が官庁統計の生産と利用の過程(客観性)を歪曲し、社会認識の素材としての統計の性質(品質)を歪めてしまっているという分析がなされたのである。ここで登場しているのは、「客観的な方法」に基づいた統計の生産と利用の過程を歪める主体としての国家(行政機構)というお馴染の構図である。
(ここで若干補足しておけば、国家が一般民衆の実態を正確かつ客観的に統計把握しようとするのに対し、一般民衆が統計調査に協力的でなく正確に質問に答えないという「統計調査環境の悪化」という名で今日的に語られる状況を持ち出し、国家を客観性の擁護者の側に、一般民衆を客観性の歪曲者の側に置くという操作を行い、蜷川の図式を逆転することは可能なように見えるが、蜷川理論は、そのような逆転を許さない理論的地盤に構築されていると考えるべきである。蜷川統計学によれば、そのような構図の逆転が起きるのは国家の利害が一般民衆の利害と切り離され、一般民衆の利害に対立するものとして成立しているからであり、国家が一般民衆の立場に立ち、一般民衆の立場を代表するようになれば客観性の歪曲問題は解決すると考えられているのである。蜷川理論には、国家の「民主的」変革という課題が、その理論構造のなかに当初から折り込まれているのである)
さて、このような構図を持つ蜷川統計学は、現実の官庁統計の作成過程を次のように把握することになった。統計の作成過程は統計作成主体が統計調査と呼ばれる方法(形式)を用いて対象となる客体に働きかけ、統計と呼ばれるデータ形式の数量的社会認識を客体から獲得する過程である。蜷川統計学の特徴の一つはドイツ社会統計学の流れを継承し社会観察を自然観察と異なった独自性を持つものと定義したことにあるが、自然観察は観察者が観察対象を測定機器を用いて「一方向的に」観察する過程であるのにたいして、社会観察は《見る者》(=見る主体)と《見られる者》(=見られる主体)との間の間主観的関係の場に成立する情報のやり取りの過程として把握されたのである。その結果、蜷川統計学においては、《調査主体》(=調査者)と《被調査主体》(=被調査者)との間の関係の場を典型例とするような主体間関係の場に成立する情報収奪過程として統計調査は定義されたのである。
蜷川理論にとって肝要な点は、このような主体間関係としての統計調査という見解を「社会的集団=大量の自己表出過程としての統計調査論」というベースにある論議に組み込むことであった。そこから、次のような見解が生まれることとなった。「正しい、信頼性のある」統計の獲得のためには「客観的な統計方法」の論理に即くことが必要であり、それを可能とする条件は統計作成主体は自らの主観性を可能なかぎり消去することである(注12)。しかし、現実の社会的な利害対立を含んだ社会的・歴史的条件は、そのような主観性の消去を不可能なものとする。様々の主観性が対立しあい、騙しあい「客観性」を歪曲しながら「客観性」の獲得に向かって歴史は終焉に向けて展開していくのだからである。それがヘーゲル流の歴史性なのである。蜷川統計学が《生産》という概念を語るとき意味されているのは、このような生産の場なのであった。さて、このように統計生産が定義されるとすれば、蜷川統計学にとって生産とは、第一に、目的意識を持った主体の行為であり、第二に、対象(客体)から物事の本質を抽出することであり、認識とは抽出された本質のことだということになる。蜷川理論が言う「客観的方法」とは「正しい」抽出方法を規定したものであり、統計の作成・利用主体としての国家は「客観的方法」を歪曲する主観性の場なのである。
ところで、この第二の生産の定義に示された認識観は金鉱石から純金を抽出する過程を思い浮かべると良く理解できるかもしれない。認識主体が客観的対象(実在の金鉱石)に働きかけ、その内部に「一部露出しながら隠されてる」認識(純金)を取り出す過程として認識過程が理解されるのである。この認識観に特徴的なのは、認識過程を認識主体(主観)と認識対象(実在対象)との間に成立する過程として理解し、実在対象のなかに「露呈しつつ隠されながら」存在(実在)する「本質的」部分を分離し取り出し言語表現化したものが客観的認識であると考えることである(このことは帰納法をイメージすると分かりやすい)。この認識観のなかでは、客観的な認識結果は認識過程に先立って既に客観的実在のなかに存在しており、認識労働が行うことは既に存在している認識結果を分離,取りだし言語表現化することで、眼前に提示することだけである。(注13)
しかし、科学哲学の歴史を参照すればすぐに分かるように、認識論の歴史は「既に存在する認識結果を取り出すことは本当に簡単なことなのか」をめぐる論議の歴史であった。観察や言語表現は本当に透明な活動・存在なのだろうか。捕らわれない純真無垢な態度で自然に対面すれば自然は真の姿を本当に現すのだろうか。例えば、ヒュームの認識の問題からマッハの認識批判論へ、そして論理実証主義から言語論的転回へと至る過程で実証主義的な社会科学は「観察された事実(観察言語によって記述される事実の言明)」と「正しい言語の使用」に認識の絶対的な基礎を置くことにしたが、その土台となる「観察言明」や「正しい言語使用」の地位(そもそも観察言明や正しい言語使用というものは存在しうるのか、存在するとしても、それは何を表現しているのか)が曖昧で不安定なものであることから、その「客観性」への主張の「正しさ」はその基礎から絶えず掘り崩されてきたのである。実証主義の科学は、その基礎付けをめぐって絶えず「実在論(例えば「三角形」という概念は我々の主観的意識の外部に実在する実在世界に根拠をもって実在している)」と「反実在論(「三角形」という概念は我々の主観的意識が作りだしたもので、実在の世界には対応物は実在しない)」へと分裂し、その狭間で漂流してきたのである。他方、このような実証主義の科学観に異議を申し立ててきた現象学は両者の対立を《私と世界(環境世界)との関係》という関係性の場を設定することで解消しようとした。世界の意味は、実在の世界のなかにも、私の主観的意識のなかにも実在せず、ただ両者の関係性の場のなかにのみ立ち現れ実在するのだと現象学は考えたのである。「三角形」という概念は、主観の側にも、実在の側にも在るのではなく、主観がある志向性をもって世界(対象)と向かい合うときに、世界(対象)の側からの応答として「存在」するのだと考えたのである(「三角形」という概念は人間精神による構築物であるとしても、その概念が指示する対応物が実在の世界の側になければ存在しないだろう)。
蜷川統計学を他と区別する種差的性質のひとつは、その「唯物論的」性格にあると言われるが、この論争点への介入を蜷川統計学は「唯物論」の哲学を武器として行ったのである。ブハーリンの『史的唯物論』やレーニンの『唯物論と経験批判論』との係わりなどが指摘されているが、蜷川虎三における「唯物論」がどういうものなのか実は明確でない。しかし、少なくも戦後蜷川統計学の流れのなかで見れば、実在論的な反映模写論的認識論としての「哲学的唯物論」と「存在が意識を規定する」という「史的唯物論のテーゼ」が、その唯物論の内容であったことは間違いないところである。後者に関しては、「存在(対象)が方法を規定する」というふうに読み替えられ、統計方法を唯物論(唯物弁証法)の諸規則によって基礎づける試みが内海庫一郎よって行われ多くの成果を生んだが、ここでは前者の「反映論的認識論」としての「唯物論」が問題である。
反映論的認識論は実在論を基礎とした認識の理論であり、認識主観の外部に客観的実在が存在しており、認識主観は対象として設定された客観的実在の本質的部分を非本質的部分から分離し思考の秩序の中に写しとることができるとする認識観である。統計を例にとれば、認識対象(実在の対象)の側に認識過程に先立って既に統計数として表現されるべきもの(例えば失業者集団)が存在しており、認識としての統計数は対象の側に既に実在している事物(失業者数)を統計言語的に表現したものだと考える認識観である。この認識観に基づけば、統計調査とは本質的部分(失業者集団)を非本質的部分(他の人口諸集団)から分離・抽出し、統計言語に写し取る装置であり、もし、この抽出装置が上手く働かなければ、統計の正確性に欠陥が生じ、この抽出装置を用いる認識主体(統計調査者)の利害・関心が不純であれば、統計の信頼性が傷つくということになるだろう。したがって、この認識論にとって特に重要なのは、「正しい」抽出装置を定義することと同時に、この抽出装置が正しく働く条件を定義することである。例えば、蜷川統計学は統計の社会性と歴史性について強調しているが、それは、この条件の定義に係わっているのである。統計の歴史性とは調査という認識抽出装置が歴史的に形成されたということであると共に統計調査の対象(実在)自身が歴史的に形成された現実(実在)であることであり、それを抽出・反映した統計も歴史性を持たざるえないということである。蜷川統計学においては、そうした歴史性が統計の社会性(階級性)を生み出すのである。歴史のなかに埋め込まれた認識主体(統計調査者)が社会のなかで一定の階級的地位にあり、その階級的利害のもとで敵対する諸階級との利害関係を調整しながら調査を行うということ、その結果、調査結果としての統計(認識内容)に一定の階級的利害関係が反映されるというのである。
既述のように統計利用者の統計学である蜷川統計学にとって重要なのは、主に官庁によって作成され提供される統計データの評価(の基準)を与えることであった。蜷川統計学は、これを統計の正確性と信頼性を検討する問題として定式化した。ここで重要なのは、その正確性と信頼性の論議を支えている反映論的認識論に固有の認識評価の基準は何かを確認することである。一般に、認識論による認識評価は「客観性」・「真理性」あるいは「有用性」という概念を機軸に置いてなされる。反映論的認識論は、認識対象(客観的実在)の側に既に有るものを取り出すこと(=写し取ること)が認識過程であり、写し取られたものが認識であると考える。だから、この認識観のなかでは、「正しい仕方で」写し取られたのかどうか、あるいは、写し取られたものが対象物を「正しく」写しているのかどうか、が評価基準となるのである。
だが、ここで認識生産物を評価するのに対象物と照合するという後者の戦略をとるとすれば問題であろう。なぜなら、対象物を何の媒介もなしに「直接に」眼前に置くことなどできないからである。我々があるものを「対象物」として眼前に置くときには、そこには常に、あるものを対象として設定する一連の操作が介在しているはずであるし、ある対象物をあるものと確定し規定するときには、一連の感覚や言語の作用が働いているからである。「認識生産物を対象物と照合する」と言うとき、実際にそこでなされていることは、他の認識生産物と比較対照しているにすぎないのである。この評価戦略を採用するとすれば、経験論的実証主義のように「観察言語」によって記述された世界をありのままに写すテキストの存在を前提するか、すべての認識がそれに照らされて評価される基準となる《聖書》のようなテキストの存在を前提にしなければならないからである。いずれにせよ、この戦略は既にどこかに「正しいテキスト(教科書)」が存在していることを前提にして成立しており、学校教育の現場では通用しても、その外では通用しないのである。
そこで、ほとんどの場合、写し取りの仕方・過程が「正しければ」、その過程の生産物も「正しい」とする前者の戦略が採用されることになるのである。これが、多くの科学論で方法論が重要視される理由である。実際、蜷川統計学においても(認識)評価の基準として「正しい」認識の取出法が想定され、当該の統計データを産出した調査が、その取出法に準拠していれば、統計データの「正しさ」が保証されるという評価戦略が採用されている。この「正しさ」を蜷川統計学は「統計の対象反映性」と呼ぶのである。蜷川統計学においては、「正しい」取出法は「正しい」統計調査法によって規定されるのだから、統計データの検討・評価とは、評価対象となる統計データが生産される過程(統計調査の過程)を具体的に分析し、その調査過程が「正しい」調査過程に準拠して行われたかどうかを検査することなのである。統計調査の過程を理論的過程と技術的過程に理論的に分離し、前者を統計の信頼性に、後者を統計の正確性にかかわる過程として叙述する蜷川統計学の統計調査方法論は、こうした検査基準として適切に働くように法文-形式化された調査過程論だったのである。しかし、「正しい」統計調査過程論・調査方法論の「正しさ」を保証するものは何かという問題は、残されたままである。特に、蜷川統計学は、「正しい」統計調査論の核心に「正しい社会科学の理論に主導される」ということを置いたが、「正しい社会科学」とは何か、その「正しさ」は何によって保証されるのかという問題は問われぬままに残されているのである。
2_2)ヒンデスの統計データ生産論と唯物論
ヒンデスは、次のように書いている。
「すべての認識と同様、官庁統計は生産物として分析されなくてはならない。官庁統計は、所与としてそのまま与えられるのでもないし、不適切なものとして捨て去られるものでもない。あらゆる生産物と同様、官庁統計はそれらの生産条件と生産用具に照らして検討されなければならない。統計生産の場合、二セットの生産用具を区別できる。《概念的》用具、すなわち諸事例の諸クラスへの割り振りを統轄する概念体系・カテゴリー体系、と社会調査の《技術的》諸用具との二セットである。.........統計データの評価、統計データのあいまいさ・不分明さ・概念的不確かさの範囲の評価は、役人や観察者の主観的な経験や彼らの《意味》・《暗黙知》・《背後にある経験》なるものへのいかなる言及も必要としない。.........ある特定の統計データのセットの利用はそれに独自の理論的問題を持ち出すだろうが、官庁統計の利用それ自体には、いかなる一般的な理論的問題も含まれてはいない.........。」(注14)
ここで述べられていることは、第一に、統計データは一定の生産過程の生産物であり、その評価は生産物という資格において、その生産用具と生産条件に照らして行われなければならないこと、第二に、統計の生産過程で用いられる生産用具(労働手段)は《概念的》用具と《技術的》用具であること、第三に、統計データの評価を調査主体(あるいは被調査主体)の主観性の場に還元しておこなう必要はないこと、の三点である。
2-2-1)統計データ生産の構造分析
先ず、第二の点から見ていこう。統計データ生産の用具を《概念的》用具と《技術的》用具とに分けるヒンデスの統計生産の理論は、一見したところ、統計調査過程を《理論的過程》と《技術的過程》とに分ける蜷川統計学の調査過程論に似ている。しかし、両者の意図は異なっている。蜷川統計学における理論的過程は、調査しようとする対象(「実在の社会的客体」)の認識に係わっており、どのような客体をどのように認識するか、その客体を統計調査の対象として実際に把握するにはどうその客体を対象規定したらよいか、どのようにそれを把捉したらよいか(誰をその客体の情報提供者とし、どのような方途で情報を提出させるか)を決める過程であり、欧米の実証主義出自の社会科学方法論が言うところの「操作化=理論的観念の観察操作可能な変数化」の過程をその一部分に含む社会認識に関わる過程であり、技術的過程から区別される独立の過程である。これにたいしてヒンデス理論における概念的用具論は、統計調査論の「手続き的過程論」としては叙述されていない。ヒンデスの目的は統計調査過程論の構築よりも、既存の調査論・調査に対する観念の批判にあるのである。蜷川統計学の主張と同じに聞こえるが、ヒンデスが強調したいのは、既存の調査論・調査に関する観念は統計データ生産における「理論労働の位置と働き」を過小に評価していると言うことに尽きる。特に強調されるのは、調査の対象を対象として規定する理論的認識労働の重要性である。統計調査が調査しようとする対象を理論的にどう定義するのか、統計調査がそのなかで行われる「環境」としての統計調査の社会的諸条件をどう認識するのかということが、統計調査と統計データの品質を決める決定的鍵であり、その問題こそ主題的に論じられなければならないとヒンデスは強調するのである。
統計技術的に言えば、ヒンデスが重点を置いて論述しているのは、統計分類と符号格付けの問題である。ヒンデスが、分類と符号格付けの問題だけに論議を限定してしまっているのは、シクレル、キセル以来の社会学における「官庁統計」論争の問題圏のなかで発言していることによる影響が大きいと思うが、それは問題にしないでおこう。ヒンデスは、1951年のインド人口センサス(の「農業従事者」の取り扱い)を例示にして、農民層の分類・符号格付けの問題を検討しているが、その際に彼が念頭に置いているのはレーニンの『ロシアにおける資本主義の発展』や『社会民主党の農業綱領』である。レーニンの社会構成体の歴史分析こそが、ヒンデスにとって社会体の構造と機能の歴史分析のパラダイムであり、統計利用の問題を考えるための基準となるテクストなのである(注15)。彼はソーナーの分析(注16)を参照しながら1951年のインド人口センサスにおける農業従事者の階層分類や符号格付け手引き書の検討を行いながら、統計の品質を決める決定的要因は理論的労働(概念的用具)であることを主張している。そのエッセンスを取り出せば、次のテーゼで表現できる。1951年インド人口センサスにおいて用いられた農民層分類基準(概念システム)は、インド農村の社会構成における農民層の存在形態をアティキュレート(分節化)する分類基準・概念システムとして全く不適切である。センサスにおいて用いられた分類基準は、英国における古典派経済学の三階級モデルを基礎とし、それに場当たり的な修正を加えてインド農村の社会構成に適用したものに過ぎず、資本制生産様式が浸透しているが、いまだに前資本制生産様式が確固たる地位を占めている移行期の社会構成にあるインド農業社会の社会構成を適切に捉えることはできない。その結果、人口センサスの農民層分類基準はソーナーの表現によればインド農業の社会構成の実情に適合しない《疎遠な概念》になってしまい、前資本制生産様式が支配的な社会構成に資本制生産様式の分類体系を押し付け、根本的に異質な様々の人口集団を同じ階層に振り分けてしまったり、設定された分類上のカテゴリにすんなり収まらない人口集団を大量に生み出してしまい、被調査者(回答者)の場当たり的で曖昧な自己選択や集計者の符号格付け時における過剰な判断に大きく依存する階層割り振り(符号格付け)を結果としてもたらしてしまっている。その結果、インド人口センサスの品質は決定的に悪いものになってしまっているのである。
ヒンデスが、統計生産上の理論的労働、とりわけ「理論的概念を統計観察可能な概念に変換する操作化」の過程(狭い意味での統計調査の理論的過程)に論理的に先行する「厳格な意味での」理論的労働に統計の品質を決める決定的契機を置いたということは、それまでの伝統的な統計調査論が問題の圏外においてきた理論的労働の契機を統計の品質を決める決定的要因におくということであり、挑戦的な主張だったのである(注17)。統計は「正しい」社会認識を生み出す理論に主導された統計生産過程に基づいて作成されなければならないのである。こうしたヒンデスの主張は、蜷川統計学のそれに非常に近いという印象を与えるものである。蜷川統計学も「正しい社会科学の理論」に基づいた科学的(客観的)統計調査を統計調査の規準として想定していたからである。
既述のように、蜷川統計学は統計調査の過程を理論的過程と技術的過程とに分けた。それに対して、ヒンデスは統計調査の過程において働く生産用具として《概念的》用具と《技術的》用具とを区別した。決定的に異なるのはヒンデスにおいては過程は区別されないということである。ヒンデス理論においては二つの生産用具の働きによって二重に分節化(入れ子状に分節した連接化)され、構造化された同一の生産過程のみがある。こうしたヒンデスの見解は、調査手続論としての弱さと同時に、蜷川統計学にたいし決定的な優位さを持っている。蜷川統計学では統計調査過程は規範的方法論として叙述されたこともあり、理論的過程は技術的過程と分離され、技術的過程に時間的に先行する過程として論じられる傾向があったからである。理論的過程は、統計調査の性質を決定づける統計調査の支配的過程であり、統計の信頼性を決める過程である。技術的過程は、統計調査の従属的な過程であり、理論的過程によって構想された調査過程を忠実に運用し、実現する過程、具体的には、調査票の設計と運用を行い、調査結果を集計・製表化する過程とされたのである。このように定義された技術的過程は統計の正確性を決める過程であり、あらかじめ理論的過程において決められた「数え上げられるべきもの」を「正確に」数え上げる過程である。ここにあるのは、構想と実現というおなじみの近代合理主義思考の図式である。これにたいしてヒンデス理論では、概念的用具を駆使する労働は技術的用具を駆使する狭義の調査労働と相互に入れ子状に組み合って作動すると考えられている。蜷川統計学では技術的過程の問題(統計の正確性の問題)として処理されるレスポンスエラーや符号格付けミスの問題は、ヒンデスにとっては何よりも先ず、理論的(概念的)な用具の問題として考えられるのである。調査しようと思う事柄を調査対象として理論的に明確化し定義付け、調査がどのような社会的・技術的条件の下で行われるのかを精確に把握する理論的労働が誤回答や格付けミスの種類や範囲や発生頻度を最終的に決めるのである。
2-2-2)統計データ生産の《主体》
先に引用したヒンデスのテクストで主張された第三の論点は、統計データの品質を調査主体(あるいは被調査主体)の主観性に還元して評価する必要はないということであった。この主張は、強く言えば、統計生産において《過程の主体》は存在しないということである。調査者や被調査者は過程のエージェント(担い手)であって、主体ではない。すべての社会的過程と同様に過程の担い手は、担い手として相応しい(あるいは相応しくない)働き手であるためには主体化(サブジェクション=服属化)され《主体の形態》をとる必要があるが、原因と結果を取り違えてはいけないのである。過程の性質は主体の意思や目的によって定義されるのではなく、主体の目的や意思が過程の性質によって定義されるのである。統計の信頼性や正確性は調査主体や被調査主体の利害や意思によって「歪められる」という形態を取ることはあるとしても、統計の信頼性や正確性を調査主体や被調査主体の目的・意思や利害に還元して説明してはいけないのである。ある歴史的な社会構成のなかで《統計的》と形容される数量的社会情報装置が歴史的・社会的に形成され、社会のイデオロギー装置・認識装置として社会形成に構成的に関与し、機能しているという事実の分析が、統計の信頼性と正確性の性質と範囲を説明するのである。
2-2-3)統計データ生産の理論と統計データの合理的評価
ヒンデスの中心となる論点は、統計データは生産物として評価されなければならないということであった。生産物として評価するということは、それを生産物として産出した生産過程によって評価するということである。統計データの評価には、統計データを生産した過程の分析が必要なのである。先に確認したように、ヒンデスにとって生産過程は主体の過程ではない。だから統計データの評価の基準を《主観的なもの》に置くことはできない。この点で実証主義的な統計論も反実証主義的な統計論も《主観性》ないし《共同主観性》の哲学に基礎を置くかぎり、ヒンデスにとって受け入れがたい。《主観性ないし共同主観性の哲学》に基礎を置く統計論は、結局のところ、統計データの信頼性や正確性の問題を主観性の問題に還元してしまうからである。同様に、蜷川統計学の統計の社会性(階級性)論も受け入れがたい。蜷川統計学における統計の社会性や階級性は、結局のところ、集合主体としての社会集団(社会階級)の主観性(イデオロギー)に還元されるからである。例えば、資本主義国家の官庁統計は調査主体としての国家の産物であり、資本主義国家は資本家階級の国家であるのだから、官庁統計は集合主体としての資本家階級の主観性を反映したものになるだろうという一般的帰結に還元されてしまうのである。
ヒンデスが統計生産のモデルとして考えているのは、マルクスが「1857年の経済学批判序説」や『資本論』で定義した生産過程の理論である。生産過程は労働過程と労働過程がその下で組織される生産の社会的諸関係によって編成された一つの社会的過程である。労働過程は、一定の技術的諸関係の下で労働者と労働手段と労働対象(素材)を結合し、一定の素材を一定の生産物へと加工(変形)する過程であり、自然・科学技術・人的資源など歴史的に形成された物質的・技術的条件によって規定された歴史的メカニズムである。そこでは労働力(労働者)は労働過程の物質的・技術的条件に組み込まれた担い手であり、過程の主体ではない。過程の性質を決めるのは過程そのもの、その過程が歴史的に形成された社会的全体のなかで働く様式、社会全体のなかに占める位置・働き・及ぼす効果である 。労働過程は一定の生産の社会的諸関係のもとで組織され、重層決定(連立方程式の解が一義的に決まるように優決定)されて働く。労働過程に社会的性質を与え、生産過程として編成するのは、この生産の社会的諸関係である。
以上のように生産過程を定義すれば、統計データの生産過程は、一定の歴史的に形成された社会的諸関係の下で、素材として設定された直感と表象(さまざまな定型的・非定型的情報など)を統計数値・統計表(統計情報)へと加工(変形)する過程であると定義することができるであろう。先述のように、ヒンデスは、そこで用いられる労働手段に着目して統計の生産過程を分析しているが、それは労働過程の性質を決める支配的要因は労働手段であるという構造主義的テーゼに従っているからである。彼は、統計生産に用いられる労働手段、特に概念的用具の働きに注目して統計生産の過程を分析し、認識主観の主観性に頼ることなしに、統計データの認識論的な価値(社会科学的認識における価値)を統計生産の過程のうちに合理的に説明し、測定・評価しようとしているのである。ヒンデスによれば、統計の評価は、統計調査に関与した諸主体の「意識(意味付与過程)」のなかにではなく、その統計を生産物として産出した具体的・歴史的な統計生産の過程の具体的・歴史的分析によって行われなければならないのである。
2-2-4)統計データの合理的評価の理論と批評の観点
統計は《概念的》用具と《技術的》用具との結合による生産物であるとするならば、統計の評価は《技術的》用具に由来する誤差や不適切だけではなく、《概念的》用具(概念的生産手段)に由来する不適切(蜷川理論による信頼性の問題に近いもの)を問題としなければならないだろう。しかし、技術的理由による問題は、事柄の性質上、捕らえるべき対象が決まっており、それを技術的制約の中で「正確に」捕らえていくことだけを考えれば良いのであるが、概念的理由による問題は、捕らえるべき対象を決めることに関連した問題であり、しかも先述のように技術的要因による問題の種類と範囲を決める問題でもあり、一層複雑な問題を抱えている。
ここでヒンデスは、議論のなかに新しい次元を導入している。捉えられるべき対象を捉えているかどうかは、その統計データがそのなかで認識素材として用いられている認識(論証・立証)過程のなかで、認識過程が割り当てた論証上の(証拠提出上の)働き(役割)を満たしているかどうかによって決まるとする統計の合理的評価に関する論議である。統計の評価は当該の論証(立証)過程のなかでの証拠としての価値によって決まると言うのである。統計の評価は当該の統計がそのなかで用いられる論証(立証)過程の関数として決まるのである。統計の認識論的価値の一般的評価は存在しないのである。ヒンデスは、こうした認識論的価値の評価作業を《批判的=批評的な》作業と名付けている。
ヒンデスは、この点を例示するために1951年インド人口センサスを1950年前後のインド農村の社会的構成のマルクス主義的分析との関連で検討している。マルクス主義的な社会分析のプロブレマティックからすれば、インド農村の社会構成は資本制生産様式の発展という観点から分析され、資本制的生産様式の要素と種々の非資本制的諸要素との歴史的結合として概念把握される必要がある。そこでは農村部への商品関係(市場経済)の浸透の形態と範囲を把握することが分析の重要課題となり、それを可能にする調査項目・分類体系をもつ人口センサスが要求される。しかし、ヒンデスによればインド人口センサスは、農村社会における商品関係と非商品関係とを区別する調査項目も分類体系も持っていない。だから、インド人口センサスはマルクス主義的な社会構成体分析の論証(弁論)過程に証拠として採用・利用することはできない。これがヒンデスによる評価である。
しかし、人口センサスを無批判に採用・利用できないとしても、批評家としての距離を保ちながら批判的に利用することはできないのだろうか。証拠書類としての限界を踏まえながら、限界内で利用することは可能ではないか。そこでヒンデスは、さらに先に進んで、次のような批判的な利用法について提起している。調査過程で用いられたカテゴリーと公表された報告書で用いられた分類区分とは異なるのが通常である。調査過程で活用された情報は、製表化や符号格付けの分類作業のなかで失われるものである。こうした場合には、両者のカテゴリーを関係づける対応規則を知ることができるならば、理論的に重要な情報を再構築もしくは推測することが可能になるだろう。こうしたヒンデスの統計利用に関する提案は、「活用できる統計の厳格に理論的な利用を企てた者には、お馴染のことだ」と彼自身ことわっているように、特に新しいものではない。蜷川統計学が提起する統計利用の形態の一つである「統計の批判的な加工的利用」をヒンデスは提起しているに過ぎないのである。ヒンデスの統計の合理的評価の理論の独自性は、別のところに探さなければならないのである。
2-2-5)ヒンデスにおける批評の観点と唯物論
ヒンデスによる統計の合理的評価は、当該の論証過程のなかで求められている役割(機能)を当該の統計データが満足できるものなのかを、そのデータの生産過程にまで遡って検討することであった。だとすれば、統計データの評価はその統計の生産過程を《客観主義的》に分析することでは達成できない。統計の評価は、その統計がそのなかで用いられる個々の論証過程との関連で、その関数として決まるのである。だとすれば、統計の評価は一つではなく、複数であることになる。実際、ヒンデスはインド人口センサスをマルクス主義的社会分析の関数として評価するだけでなく、チャヤノフの小農経済論との関連でも評価付けできると指摘している。ヒンデスの発言を引用すれば、「科学的目的での社会統計の評価付けは、いつも必ず、ひとつの理論的行使なのであって、異なった理論的問題設定は所与の統計データセットにたいする異なった、時に相互に矛盾する評価付けを生み出すに違いないのである」(注18)。もっとはっきり言えば、マルクス主義の問題設定からすれば、資本を不変資本と可変資本に区別する分類体系を持つことが統計に要求されるが、資本家的合理的実践の問題設定からは、固定資本と流動資本に区別する分類体系が必要とされるだろう。統計の合理的評価は、このように当該の統計データが利用されるコンテキスト、そのコンテキストを基底部で決める問題設定との関連で決まるのである。
このように統計の合理的評価付けの理論を見ていくと、統計の合理的評価付けの理論と先述の《疎遠な概念》論との関係付けという問題がでてこよう。合理的評価付けの理論は、複数の問題設定の存在を権利として承認し、それぞれの問題設定との関連で統計の認識論的評価が決まるとするものであったが、《疎遠な概念》論は、当該の統計データが問題となっている事態を「正しく」対象として設定し把握しているかどうかを問題としているからである。もし問題設定の複数性・多元性を承認するとすれば、「正しい」問題設定の群と「間違った」問題設定の群を区分することが問題となろう。しかし、「正しい」と「間違った」を区別する基準はどこにあるのだろうか。
ここで蜷川統計学の「正しい社会科学」に関する主張が思い起こされるかもしれない。蜷川統計学では「正しい社会科学の理論」に基づくことが「正しい」統計調査・統計利用の条件だとされていたからである。蜷川統計学における「正しい社会科学の理論」が何を意味し、何を指示しているのかは論議の別れるところだと思うが、同じ目的(例えば、日本の勤労者の労働時間は国際的に見てどの位の水準にあるか)で統計を利用するという条件下で、利用者が「正しいと思っている」理論と官庁が統計を作成するにあたって「正しいと思い」指導理論とした理論(実際には当該事象を規制する諸法制によって決められる場合が多いであろうが)とが「一致」しないときに当該の統計の「信頼性(妥当性)」が疑われるだろうという点では、見解が一致するかもしれない。しかし、「正しいと思うこと」と「正しい」は同じでない。「正しいと思うこと」が「正しい」の条件であるとしたら、主意主義と相対主義の泥沼にはまり込むこととなろう。「正しい手続き」に従っていれば「正しさ」が保証されると考えれば、「正しい手続き」の「正しさ」は何が保証するのかという同様の問題に送り返されるだけであろう。蜷川統計学は実在論に基づく「反映模写論的認識観」に定位することでこの問題を切り抜けようとしたのであった。
それに対し、ヒンデスの統計生産論は実在論や「反映=模写論的認識観」の立場には定位しない。統計の生産が強い意味で「生産」であるとしたら、それはある素材を他のものに変形・加工することであり、既にあるものを「目の前に置くこと」ではないからである。統計の生産は、ある素材(調査対象者として指定された個人・団体が保持している定型的ないし非定型的情報)を統計的表形式をもった定型的数値情報へと変換する過程であり、生産物としての統計的数値情報はそれに固有な社会的効果(統計的な社会認識効果など)を社会体内で産出するのである。こうしたヒンデスの統計生産論・認識生産論の立場から「反映論的認識観」を見れば、その決定的な問題が浮かび上がってくる。それと同時に、ヒンデスの認識生産論の姿がより明確に浮かび上がってくるはずである。
「反映論的認識観」を検討するために、先に取り上げた金鉱石(=実在の複雑錯綜した世界)から純金(=認識)を抽出する認識モデルを引用しよう。すぐに気づくことだが、その認識モデルが問題であるのは、金鉱石から純金(=認識)を抽出するというとき、「観念」と「観念の外部の世界」の区別と関係の問題を曖昧にしつつ、そこでは既に「金」という概念(金の認識)を前提してしまっているということである。この認識観のなかでは、認識されるものは認識過程が始まる前に既に認識されており、その対応物は実在の世界に既に実在していると想定されるのである。なぜこのようなことが起きるのかと言うと、この認識モデルのなかでは観念の内部での観念的対象の生産過程が観念の外部の実在対象のなかに投影され、観念の外部の実在過程と取り違えられてしまうからである。その結果、認識(の内容)は実在対象のなかにその本質部分として含まれていると想定されてしまい、実在の対象と認識の対象がごちゃまぜにされてしまうのである。このような認識観においては、認識実践が意味を持つとするならば、せいぜい誤った様々の観念を注意深く取り除き、そこに既に在る真の姿(認識)を暴きだすことだけだろう。しかし、過ちを正せば真の(神の)姿が顕現するといった種類の操作が可能となるのは、真の姿が既に認識されているときだけだから(なぜなら何が過ちであるかを決めるのは「真」の姿なのだから)、結局のところ認識実践とは既に識られている「正しい」認識の立場に立って「誤った」観念を攻撃し正すことだということになり、悪しき独断論の迷宮に迷い込むこととなろう。その認識観のなかで欠落しているのは、厳格な意味での理論的労働の位置と役割、独自性を承認することである。厳格な意味での理論的労働の地位を復権させ、今ここに与えられてる様々の観念を攻撃し正す論弁的実践(戦闘)が、その戦闘のなかで新たな論弁的形式と内容を産出し、新たな社会的、認識的効果を産出していくという認識観に立つことが必要なのである。
先述の認識モデルのイメージを継続して言い換えれば、「金」(概念)は「金」として認識される理論的労働過程に先立って「金」(概念)として存在しているわけではないということを承認することが必要なのである。「金」が「金」として存在するためには、「金」を「金」として認識し、理論的対象として練り上げる理論的・概念的労働が必要なのである。なるほど《実在の金》は我々の観念(意識)とは関係なしに独立に《金鉱石》のなかに今も昔も存在し続けてきたと言うことは可能だろうが(但し、ここで「金」の例を「点」や「線」の例に置き換えると簡単ではなくなるだろうが)、そのことと「金」が「金」として認識されるということは全く別のことなのである。人類は「黄金色をした鉱物」を欲望の対象として設定し、「金」と名付け、自然界の鉱物から「金」を抽出してきただろうし、近代科学(化学)は「金」を「元素の周期表」や「原子量表」の概念(分類)システムに組み込み、「元素」の一つとして対象設定(概念化)することで、「純金」という表現に具体性を与え、金鉱石からの「純金」の抽出に現実性を与える基準(混じりのあるものと無いものを区別する客観的基準)を与えてきただろう。「金」という概念や「金鉱石から純金を析出する」という観念は実在の「金」に属しているのではなく、「知・観念・理論」の領土(秩序)に属し、観念・理論の労働によって作りだされた(生産された)のである。認識労働(過程)は、実在の「金」(の本質)を反映模写することによって「金」という概念を作りだし実在の「金」を認識するのではなく、観念的・理論的な労働によって、様々の観念・概念システムが交差する思考空間の中に「金」という観念・概念を産出することによって、その観念の効果(作用)として実在の「金」を認識していくのである。認識労働は、それがそこに所属する社会体のなかに「認識(「金」という概念)」という実在の実践領域(社会体を構成する一つの領域)を付け加え、他の社会的実践と入れ子状に分節化することによって、その効果(社会的・技術的効果の一環としての認識効果)として実在を認識し、認識された実在を「現象工学的(バシュラール)」に操作可能な対象として設定していくのである。このような認識観をマルクスは《批判=批評》と呼んだが、ヒンデスはアルチュセールに依拠しつつ《認識の生産》と呼んだのである。
このような認識の生産観に基づいたとき、「正しい」と「間違った」を区別する基準はどこにあるのだろうか。認識(統計)の生産が社会体内で行われる生産(社会的実践)であり、独自の社会的効果をもつとするならば、それは物質性(他の何かに還元できない独自性)を持っているということである。認識(統計)を生産するということは、反映論的な認識論が想定するように《既にあるもの》に言語の形式を与え「目の前に差し出す」ことではなく、実在の世界に《認識(統計)》という新たな実在の次元(水準・審級)を付け加え、実在の世界に入れ子状に分節化させ、実在の世界に効果を及ぼし、実在の世界を変形し形づくるということである。社会体に経済の水準(審級)や政治の水準(審級)や法律・イデオロギーの水準(審級)があるように、認識(統計)という実在の水準(審級)があるのである。だとするならば、「正しい」と「正しくない(間違った)」の区別は伝統的な認識観が想定するような意味での純粋に認識論的な区別ではなく、社会的な次元をもった区別であると考えなければならないだろう。また、社会体の様々の水準(審級)間に照応・非照応があるように認識の水準と他の水準との間にも照応や非照応(ズレや断層)があると考えなければならないだろう。社会体を構成する諸実践は、そのような認識の次元が社会や技術に及ぼす諸効果にたいする評価(評価をめぐる闘争というものが当然あるだろう)としてある認識(統計)に「正しい」とか「正しくない(間違った)」というラベルを付けていくのである。だとすれば、我々にとって必要なことは、悪しき独断論に陥ることも、無原則な相対主義に陥ることもなく、「(科学的)正しさ」をめぐる歴史的に進行中の今ここにある論弁的諸闘争に参加することなのである。
III. 利用者のための統計学から公民権のための統計学へ
ヒンデスは論議を「社会科学における統計利用の問題」に限定し、統計評価の問題を統計の認識効果の問題に制限しているが、前章で確認したように、そのように限定したとしても統計の評価の問題は、結局のところ、社会的実践の一つの水準(審級)としての統計生産が社会体のなかで生み出す諸効果の評価問題とならざるえない。だとすれば、《統計利用者の統計学》として構想されたヒンデス統計理論の限界も明らかである。統計の認識論的価値の評価問題は、社会体の様々の水準(審級)間の関係の場に開かれているからである。統計の生産と流通と利用が社会体内で行われる社会体を構成する社会的実践であり、社会体を構成する他の様々の諸実践の作用効果を受けつつ、それ自体、社会体の諸実践に様々の現実的効果を及ぼす物質的実践であるとするならば、統計生産・流通・利用は統計が生み出す社会認識効果に限定することはできない様々の社会的効果を持っているはずであり、統計学が統計についての科学であるとするならば、統計の生産と流通と利用が社会のなかで果たしている様々の役割・働きを解明しなければ統計の認識論的価値の評価も定まらないからである。例えば、国民経済計算は政府による一国的規模での経済・社会のマネジメント様式(マクロの政策的変数による社会と経済の管理様式)の問題と密接に結びついているし、人口の諸区分は「自然的」な区分などでは全くなく、国家による人口のマネジメントの問題(例えば諸家族・諸個人を様々の社会集団として管理する)と密接に結びついており、その諸区分は国家の社会政策や地域・産業・経済のマネジメントと密接に結びついているし、人口センサス(国勢調査)は単なる一国における総人口の数え上げの装置(いかに正確に数え上げるか)ではなく、国家と国民の形成のための政治的・イデオロギー的装置であり、内と外に向かっての国家の領土(行政権の及ぶ範囲)の画定のための装置(国家の暴力装置)として機能してきただろうし、領土に定住する諸個人を国民ないし外国人として呼びかけ主体化する「(国家の)イデオロギー装置」(アルチュセール)としても機能してきただろう(注19)。一般に、統計は近代国家の形成と国民形成のための政治的・イデオロギー的装置として機能してきたのである。統計の認識論的価値も、これらの機能との関連で評価されるべきものなのである。だとすれば、社会科学としての統計学は、《利用者》という水準に留まることはできず、統計の生産者の水準にも係わらなければならないだろうし、統計の生産と流通と利用に効果を及ぼし、かつ統計の生産・流通・利用の諸過程によって効果を受ける社会体の諸実践の水準に構成的に係わらなければならないのである。利用者の統計学でも、生産者の統計学でもなく、統計的実践が社会の諸実践に構成的に関与する社会的な場に定位し、統計的実践の社会的働きを「批評的に」評価できる統計学を我々は実践しなければならないのである。
このような実践の場として本稿は「公民権のための統計学」という場を提起したい思う。本稿が、このような場の必要を考えるときに、念頭にあったのは英国における第二次大戦後の官庁統計政策への関心と情報化社会におけるプライバシー問題との係わりであったので、最後に、この二つの問題を取り上げ、紹介し、その問題の所在を示唆することで、開かれた形で本稿を終わることにしたいと思う。
1.英国ブレア政権の統計政策と公民権の統計学
英国における労働党ブレア政権の登場(1997年5月)は、英国統計政策史にとって一つの時代を画するものとなるだろう。英国では、サッチャー政権下の「統計抑圧政策」で1980年代に官庁統計は大きな打撃を被ってきた。「情報は第一義的には政府がその任務を遂行するために必要としているから収集されるべきなのであって、公刊のためにではない」(1980年の D.レイナー報告)というサッチャー政権の「官庁統計政策」の基本原則は、「政府による政府のための統計(の作成と利用)」という立場を根幹に置き、政権にとってさしあたり必要がないと見なされた分野の統計予算と人員は大幅に削減され、その結果、英国における官庁統計の品質は決定的に低下したのである。危機感を持った王立統計協会(RSS)は1989年に作業グループを設置し、官庁統計家と連携し統計の品質向上のための提言を行い、巻き返しを行った。その結果、レイナー原則に基づく統計政策は、1990年11月のサッチャー政権の崩壊とともに変更され、メジャー保守党政権の下で官庁統計の建て直しが行われたが、労働党ブレア政権の登場により、官庁統計政策の基本原則の抜本的変更が明瞭になったのである。
「公開性と信頼に基づいた政府と公民(市民)との新しい関係」の構築を政権の基本理念とするブレア政権の統計政策は、1998年2月に議会に提出されたグリーンペーパー:Statistics: A Matter of Trustによって明確に示されたが(注20)、「integrity(圧力に屈しない気高さ)」と「national(全国民的な)」という二つの基本原則に基づいている。ここでインテグリティは、サッチャー政権下での統計への干渉政策と統計の政治的道具化への批判を含意しており、あらゆる政治的な圧力・干渉からの官庁統計の独立性を提唱しており、ナショナルはサッチャー政権の「政府のための政府による統計」という原則への批判を含意しており、国民に開かれた「公共的な」政治的・社会的な空間に置かれた官庁統計の作成と利用の実践を提唱するものである。ブレア政権の官庁統計政策は、様々の社会的諸勢力の利害が衝突しあう「社会的空間」に官庁統計の作成と提供と利用の実践を置くことで、換言すれば、時の政府の政治的干渉や行政諸機構の利害関係から相対的に自律した「公共的空間」に統計情報システムをおくことで、統計情報装置に社会の信頼性を取り戻し、統計に「公共性」を確保しようとしているのである。例えば1996年に創設されたThe Office for National Statistics (ONS) の制度的確立と機能強化など、そのための制度的枠組を作ることが政権の課題なのである。こうしたブレア政権の統計政策は、官庁統計を「政府による、政府のための統計」ではなく、様々の利害を持った社会的勢力が対立しあう力の場に開かれた空間に「統計の作成と利用」を置くものであり、このような力の場に身を置く統計学を本稿は「公民権のための統計学」と呼びたいのである。そのような統計学は、もはや「利用者の統計学」ではあり得ないであろう。なぜなら、今日、統計学は、「(国家に抗する)統計利用者」だけに係わるのではなく、「(時の政治的・社会的権力に抗する)統計生産の場」に深く関与しなければならないからである。
2.情報化におけるプライバシー問題と統計学の課題
「公民権の統計学」は、社会的に権威付けられた「公共的性質」を持った社会情報を広く社会に提供する制度的枠組に関与するものである。その意味で、それは社会に責任を負っている諸団体の情報の公開性や活動内容の明示といった概念や情報自由法(情報公開法)などの法的な枠組みと構成的に係わるものである。しかし、情報の公開性や活動内容の明示(説明責任)は、その内容に、諸組織・団体(政府行政組織、民間営利・非営利活動団体)がその活動において「どのような情報を、いつ、どこで、誰から、どのような仕方で収集し、どのような仕方で蓄積・保管し、どう利用するのか、また蓄積された情報(データベース)をどのように処分するのか」といった事柄を含まなければならないものである。その意味で個人情報(プライバシー)の保護は、情報の公開性と活動内容の明示を前提として要求するのである。
今日、電子情報ネットワーク社会化のなかで行政諸組織や民間の諸団体によって諸個人・諸団体の情報が系統的に収集され、電子情報化されたデータベースのなかに蓄積され、様々のデータベースが相互にリンクされ、様々の分野で活用されはじめている。このような状況は、統計の生産と流通と利用にとって新たな可能性を開くものである。しかし、社会は多用で膨大な情報の網の目の下で透明化され、諸個人や諸団体はその網の目のなかで、操作の対象として設定され、処理される(注21)。社会科学としての統計学は、こうした情報化社会の「暗闇」を照らし出し、諸個人や諸団体が操作の対象となるのではなく、社会的・政治的・経済的な権利主体として、すなわち公民権を持った公民として社会に構成的に関与することができるように手助けできる知識でなければならないであろう。
こうしたことは、統計学が《統計利用者の統計学》として留まることを一層、難しくするだろう。調査や業務記録によって諸団体に蓄積された多様で膨大な情報を有効活用して社会の実態を解明することは、社会統計学者の基本的な欲望であるが、調査個票や業務記録の電子情報データベース化と相互のリンケージがもたらす社会的効果、そうしたデータベースの利用に基づいた社会研究がもたらすであろう認識効果が社会に及ぼす効果を統計学は常に考慮に入れなければならないからである。《知識は正義である》というテーゼだけでなく、《知識は権力である》というM.フーコーのアンチテーゼについて同時に考えるべきなのである。今日、統計学は統計データの利用者の立場を超えて、統計の生産・流通・利用の諸過程とそれが持つ社会的効果を「批評的距離」をもって認識し批評できる立場に立つことが要求されているのである。そのような立場に立つ統計学として本稿は、「公民権の統計学」を主張したいと思うのである。
----------------------------------------------------------------------------------
注:
(1)英国マルクス主義の戦後史については、特定の視点からだが、Dennis Dworkin, Cultural Marxism in Postwar Britain: History, the new Left, and the Origins of Cultural Studies, Duke U.P., Durham (NC), 1997、を参照。 ヒンデスの理論的位置に関しては、Boris Frankel, "Confronting Neoliberal Regimes: The Post-Marxist Embrace of Populism and Realpolitik," in New Left Review 226, nov./dec.1997, 及び、捧堅二「バリー・ヒンデスの民主主義論」『密教文化』第157号(1987年1月)高野山大学、を参照。
(2)Barry Hindess, The Use Of Official Statistics In Sociology: A Critique of Positivism and Ethnomethodology, Macmillan, London 1973.
(3)手ごろに読むことができるラジカル統計学(RadStats)の文献は、J. Irvine, Ian Miles and J. Evans, eds., Demystifying Social Statistics, Pluto Press, London 1979.(J. アービン、I. マイルズ、J. エバンス編『虚構の統計』伊藤陽一、田中章義、長屋政勝訳、梓出版、1983年刊)、及び、Ruth Levitas and Will Guy (eds.), Interpreting Official Statistics, Routledge, London (UK), 1996, である。また、RadStats 以降の英国における代表的な官庁統計論として、Martin Slattery, Official Statistics, Tavistock Publications, London (UK), 1986,及びRay Thomas, "Statistics as Organizational Products," in Sociological Research Online, vol.1, no.3 (oct.1996), <<http://www.socresonline.org.uk/socresonline/1/3/5.html>> を参照願いたい。
(4)社会学における官庁統計論については、杉森滉一「統計調査と社会調査:社会学的な政府統計データ論が示唆するもの」『専修経済学論争』第31巻 第3号(1997年3月)専修大学経済学部、を参照願いたい。
(5)一例をあげれば、Michael J. Mandel, "The Real Truth About The Economy: how government statistics are becoming increasingly disconnected from economic reality," in Businessweek, Nov.7, 1994, <<http://www.businessweek.com/1998/35/z3397011.htm>> がある。
(6)Peter T. Manicas, A History & Philosophy of the Social Sciences, Basil Blackwell, Oxford(UK) 1987, 及び、Alain Desrosières, La politique des grandes nombres: Histoire de la raison statistique, La Découverte, Paris, 1993, を参照。
(7)大橋隆憲『日本の統計学』法律文化社、京都、1965年刊、p.238 を参照。
(8)デュルケーム以降の社会学における自殺研究の科学方法論上の含意については、C. Baudelot et R. Establet, Durkheim et le suicide, PUF, 1984, が入門書として最適だろう。
(9)上杉正一郎『マルクス主義と統計』青木書店、東京、1951年刊、p.51 および p.14。
(10)大橋隆憲『日本の統計学』 法律文化社、京都、1965年、p.248。また、山田満「蜷川統計学の問題構成[諸探求]:その解体への諸要素」『千里山経済学』第17巻2号、1984年2月、を参照。
(11)蜷川虎三『統計利用における基本問題[現代語版]』、産業統計研究社、東京、1988年、p. 6 。なお、蜷川統計学の形成とその特徴については、同書に解題として収められた内海庫一郎「蜷川の統計学説について」と大橋の前掲書を参照願いたい。
(12)「客観性」という観念の歴史については、Social Studies of Science, Vol.22 No.4 (Nov. 1992) に所収の諸論文を参照願いたい。また、T.M.Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton U.P., Princeton(NJ), 1995, がある。
(13)この点については、Louis Althusser, "Du <<Capital>> la philosophie de Marx," Lire le Capital, Quadrige/PUF, Paris, 1996(L.アルチュセール「資本論からマルクスの哲学へ」『資本論を読む』、今村仁司訳、ちくま学芸文庫、1996年刊)を参照。
(14)Barry Hindess、上掲書、p.12~13。
(15)ヒンデスは、Theoretical Practice, no.6, May 1972号に " Lenin and the Agrarian Question in the First Russian Revolution," という非常に優れたレーニン論を書いている。
(16)D. and A. Thorner, Land and Labour in India, Asian Publishing House, London, 1962.
(17)英語圏社会学主流派の社会調査論におけるデータ検討論は、基本的にMeasurement 論に基づいている。この論は、その言葉からも分かるように「《あるもの》を測定する(測る)」ことに関する理論である。具体的には、直接には測定できないような理論的・抽象的な概念(人間の知能でも生産性でもよい)を測定可能にする条件や操作(操作化)に関る論議で、理論的概念を測定可能で任意に操作可能な変数に変換する(あるいは、そのような変数に関係づける)ことが問題の中心となる。こうした論議が、理論的言明を観察言明に関係づけることに執念を燃やしてきた論理実証主義主義や行動主義的心理学のリサーチプログラムにつながっていることはすぐに分かることである。論議の基礎にある認識観などを無視して、あえて関連づけをするなら、Measurement 論は、蜷川統計学における大量の四要素(理論的概念)から大量観察の四要素(統計的概念)への変換についての論議に係わっているだろう。しかし、ヒンデスが理論の役割ということで問題としているのは、蜷川のいうところの大量(社会的存在)の認識、Measurement 論でいえば《あるもの》の認識の問題なのである。例えば、マルクス主義では《社会階級》や《不変資本、可変資本》について語るだろうが、非マルクス主義の社会諸理論においては、そのような対象は存在しないのである。したがって、Measurement 論が「妥当性(Validity)」と「信頼性(reliability)」に基づいてデータを検討しなければならないと言うときに、その論議は非常に重要な指摘を含んでいるとしても、蜷川統計学の「信頼性」/「正確性」論や、ヒンデスの官庁統計の合理的評価論と混同してはならないのである。なお、社会学的データ論における「妥当性」と「信頼性」の概念については、杉森滉一「データの妥当性と信頼性:社会学的測定論と統計調査論」『岡山大学経済学会雑誌』第28巻 第4号(1997年3月)、が詳細なリサーチと検討を行っている。また、Martin Slattery の前掲書は、「妥当性」と「信頼性」というデータ検討基準を上手く使った官庁統計論として推奨したい。
(18)Barry Hindess 前掲書、p.47.
(19)主権国家(国家形成・国民形成)と統計・統計学との緊密な結びつきについては、Desrosièresの前掲書を参照。また、国家のイデオロギー装置論については、L.Althusser, Sur la reproduction, PUF, Paris, 1998, を参照。
(20)グリーンペーパーは、<<http://www.official-documents.co.uk/>> から入手できる。 また、王立統計協会は、"The Response of the Royal Statistical Socity to the Government's consultation document 'Statistics: A Matter of Trust'," May 1998, <<http://rss.org.uk/Response.html>> を提出している。また、1960年代からブレア政権誕生前までの英国統計政策史については、Ruth Levitas and Will Guy (eds.) の前掲書を参照願いたい。主権国家体制における公的領域(国家)と私的領域(市民社会)の区別を越境する目的で本稿では《公民》という言葉(《市民》ではなく)を使ったが、その含意について考えるために、捧堅二「現代世界とラディカル・デモクラシー」田畑稔ほか著『二十一世紀入門:現代世界の転換に向かって』青木書店、東京、1999年刊に所収、を参照願いたい。
(21)D. Lyon & E. Zureik , eds. , Computers, Surveillance, & Privacy, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1996 に所収の諸論文、及び、ウィリアム・ボガード『監視ゲーム:プライヴァシーの終焉』田畑暁生訳、アスペクト、東京、1998年刊、を参照。